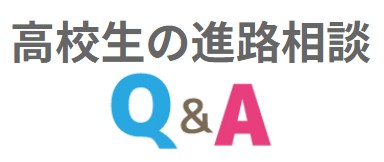Q.基本的な情報収集法とは?
まず、学校の進路指導の先生に相談する方法があります。
先生によっては丁寧に対応してくれたり、面倒だと邪険にされることもあります。
あなたの通われている学校により、対応は大きく異なりますので、先入観でものを見ないようにしましょう。もっともメジャーな情報収集の方法が、学校にある進路指導室の資料です。
大学進学を考えるなら、あなたの先輩の進路状況について調べたほうが良いでしょう。
もし難関大学などに行きたいのであれば、予備校がお勧めです。
専門的な情報は学校には置いていないことが多いので、見切りをつける勇気も大切です。またインターネットで進学希望先の学校の公式サイトや進学関係の総合サイトにアクセスしたり、
実際にオープンキャンパスに参加をして情報収集を行うこともできます。例えば、[オープンキャンパス・体験入学を探そう]というサイトでは、
専門学校や大学、短大のオープンキャンパスの検索とイベントの予約をスムーズに行うことができます。
募集学科やコース、実際のキャンパス風景の写真も掲載されているので、
より学校の雰囲気を詳しく知ることができます。
オープンキャンパス当日に必要となる持ち物や服装、AO入試についてなど、進学のための
あらゆる情報があるので、受験生はチェックしてみてください。
先生によっては丁寧に対応してくれたり、面倒だと邪険にされることもあります。
あなたの通われている学校により、対応は大きく異なりますので、先入観でものを見ないようにしましょう。もっともメジャーな情報収集の方法が、学校にある進路指導室の資料です。
大学進学を考えるなら、あなたの先輩の進路状況について調べたほうが良いでしょう。
もし難関大学などに行きたいのであれば、予備校がお勧めです。
専門的な情報は学校には置いていないことが多いので、見切りをつける勇気も大切です。またインターネットで進学希望先の学校の公式サイトや進学関係の総合サイトにアクセスしたり、
実際にオープンキャンパスに参加をして情報収集を行うこともできます。例えば、[オープンキャンパス・体験入学を探そう]というサイトでは、
専門学校や大学、短大のオープンキャンパスの検索とイベントの予約をスムーズに行うことができます。
募集学科やコース、実際のキャンパス風景の写真も掲載されているので、
より学校の雰囲気を詳しく知ることができます。
オープンキャンパス当日に必要となる持ち物や服装、AO入試についてなど、進学のための
あらゆる情報があるので、受験生はチェックしてみてください。
◎オープンキャンパスについてのよくある質問
今の時代ですから、多くの受験生がインターネットを活用して大学の情報を手に入れています。
今の時代ですから、多くの受験生がインターネットを活用して大学の情報を手に入れています。
それだけに、大学側も多くの情報をこういったサイトに載せていますから大いに参考にしてください。
お察しのとおり、この国には格差が存在します。進学先ひとつ取っても、
良い情報を手に入れているかどうかで大きく結果が変わってきます。
当然その人の将来に直結するわけですから、デマやガセでない、本物の情報を手に入れることが大切です。
新聞やテレビは信じずに、ご自身の目と耳で情報を仕入れましょう。
進学先の情報と言えば、その学校の在校生の話を聞くのも有効です。
もしあなたの学校のOBやOG がいたら、電話でアポを取って、話を聞かせてもらいましょう。
現場の生の声を聞くことが、社会で成功する秘訣です。
相手の心をきっちりと察して、手土産を持参しましょう。
社会人としてのマナーは、目上の人から教わりましょう。
Q.注意点は?
目上の人から話を聞く際には、必ず下座に座りましょう。
メモを必ず持参した上で、丁寧に話を聞きましょう。
相手にとって最も心強い味方となるのは、相手の話をきちんと理解できる人です。
進路一つとってもいろいろあるのですから、固定観念を持ってはいけません。
学校で進められていない進路には、それなりの理由がありますので、個人の主観で進路を考えないことが大切です。最後に、何でもかんでもネットから情報を仕入れないほうがいいです。
ネットの情報には悪意が含まれていますので、丸呑みにしてしまいがちな人は特に注意しましょう。
親や教師も時には役立つのですから、人生の後輩として、謙虚な気持ちで質問をしましょう。
メモを必ず持参した上で、丁寧に話を聞きましょう。
相手にとって最も心強い味方となるのは、相手の話をきちんと理解できる人です。
進路一つとってもいろいろあるのですから、固定観念を持ってはいけません。
学校で進められていない進路には、それなりの理由がありますので、個人の主観で進路を考えないことが大切です。最後に、何でもかんでもネットから情報を仕入れないほうがいいです。
ネットの情報には悪意が含まれていますので、丸呑みにしてしまいがちな人は特に注意しましょう。
親や教師も時には役立つのですから、人生の後輩として、謙虚な気持ちで質問をしましょう。