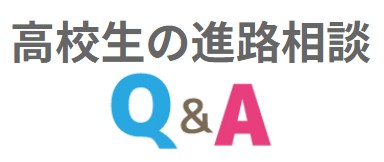部活が忙しくて勉強時間が確保できないという悩みはつきものです。ですが、部活と勉強の両立は可能です。部活と勉強を両立させて高校生活を充実したものにしましょう。
授業を最優先しよう
「部活で帰宅時間が遅くなってしまう」「平日の勉強時間がどうしても取れない」という場合、他の高校生よりも勉強時間が少ないことを自覚して、授業中は最大限、集中しましょう。
授業で習う内容をすべて覚える意気込みが大切です。
授業中に消化しきれなかった所は、印をつけておき、メモしておくと後日見返した時に効率よく復習できます。
時間を有効活用
忙しいからこそ、時間の使い方が重要になります。
通学時間などのすき間時間を上手に使おう
すき間時間とは、通学時間や何かの待ち時間など、空いているけど机に座って勉強できるほどではないちょっとした時間のことです。
そのようなすき間時間の勉強方法は単純な暗記や、その日の授業の復習です。英単語や英文法、古文単語、漢文の句形、化学式など基礎事項の暗記をやりましょう。
各教科の基礎を身につけることは大切ですが、机に座って勉強できる貴重な時間を、基礎事項の暗記に使うのはもったいないですよね。すき間時間で基礎を身につけておくことで、まとまった時間が取れた時に問題集にスムーズに進むことができ、効率的に時間が使えます。また、暗記事項は1度覚えたつもりでも、ほとんど忘れてしまうので繰り返し行い、記憶の定着を狙いましょう。
通学が電車やバスであれば、単語帳か本を読んで勉強の時間に使いましょう。スマホでプリントを撮影し、英単語や漢字などの小テストの勉強をしている高校生もいますよ。
頭の中だけで復習する
その日習った授業の内容を頭の中で思い出してみましょう。新しくなったこと、要点、理解できたこと・できなかったことなど何も見ずに思い出してみます。
ポイントは何も見ないことです。筆記用具は必要なく、手を動かすこともないのですき間時間でもできます。単純な暗記が苦手な人にもおすすめです。
頭の中だけで復習することで、要点や理解度が明確になり、家に帰ってからの勉強がスムーズに進められます。授業を思い出すことで記憶の定着にもつながるので、ぜひやってみてください。
集中できるように工夫しよう
やることがありすぎると心理的に「もう無理だ」となってしまいます。例えば、集中できなくなったら友人を巻き込んでみましょう。友人に教えることは自分の復習にもなります。自分より成績のよい友人の場合、一緒に勉強することで勉強方法や時間の使い方を学べますよ。
また、自分の部屋での勉強に飽きたら、教室や自習室、図書館など場所を変えるといいでしょう。
そして、自分の集中力の限界を知っておきましょう。数学は30分しか集中できないけど、現国なら1時間できるというように得意・不得意がわかりますよ。
少
しずつでも勉強を習慣にする
部活から帰り、食事を食べてお風呂に入ると、もう何もしたくなりますよね。スマホやテレビを見て一休みしたいというのは誰でもそうです。
しかし、勉強しないといけないのはわかっているし、やっておかなければと思いながら就寝につくというのが、ルーティンとなっていませんか。それだといつまでたっても心にモヤモヤを抱えてしまいます。
そうならないように1日15分だけでもいいので勉強する習慣をつけましょう。
勉強する上で大切なことは学習内容の定着です。たくさん勉強してもその内容を忘れてしまい身につかなければ意味がありません。忘れてしまうことを防ぐためにも毎日勉強することが効果的です。
内容は授業の予習や復習から始めてみましょう。毎日勉強することで自分が理解できていないところに気づくことができるので、それを次の日に学校で質問することができます。
また、部活を引退した後の受験生活に向けて勉強をする習慣を作るうえでも大切です。受験前になると当たり前ですが毎日勉強します。その時までに毎日勉強をする習慣ができていないと意外と苦労することになりますよ。
少しずつでも勉強することで達成感を得られますし、朝、土日、すき間時間の勉強が苦しくなくなります。まずは少しずつ勉強をする習慣を身につけましょう。
アウトプット勉強法
アウトプットとは中にあるものを外に出すという意味があり、勉強で覚えたことを思い出す、そして思い出したことを外に出す作業になります。
アウトプットには覚えた内容のテスト受けたり、自分の言葉をノートでまとめるといった方法がありますが、おすすめなのが他の人に教えることです。
人に教えることで、自分のわかったつもりになっているところが浮かび上がってきます。分かったつもりのところは自分の理解が十分ではなくスムーズに教えることができないためです。
人に教えられない部分は自分が理解していない部分ということを知っておいてください。
参考書を使って勉強する際も、アウトプット勉強法をあわせて行うことで、自分の弱点を効率的に補強できます。
そして、問題の意図を理解できるようになります。人に教えるには解説を読み込み、どうしてそのような答えになったのか理解しないと、うまく教えることができません。
作業は大変で、慣れないうちは時間がかかるでしょう。しかし、繰り返していくことで、短時間で問題が解けるようになります。
問題の意図とは、この解き方を使ってほしいということです。人に教える経験を積むことで、自然と問題の意図が理解できるようになってきます。
すぐに人に会えない場合は、独り言でもいいので、覚えたことを声に出して説明してみましょう。声を出して耳で聞くことで脳のさまざまな部位を活発に使うことになり、記憶の中にとどまりやすくなるといわれています。
スマホを封印
集中力を妨げる原因にスマホが挙げられます。自分なりに工夫をしていてもつい見てしまいますよね。
どうしてもスマホに触ってしまう場合、物理的に触れないようにするのが一番有効です。電源をOFFし、親に預かってもらう方法が確実でしょう。
スマホを持たずに図書館や学習室へ出かける方法も有効です。誘惑の少ない場所で勉強するほうが自宅での勉強より集中しやすいメリットもあります。
人目のある場所での勉強は、受験対策としてもよく知られた方法です。
効率的に勉強を進める方法
勉強を効率的に進めるにはゴールを設定し、守備範囲を決める、細分化のステップを踏むことが大切です。
ゴールを設定
事前に定期テストや大学入試の目標点数を決めておきましょう。人はゴールがなく闇雲に進めようとすると疲れてしまいます。
とはいっても、全教科100点を目指すというのは無理があるので、ここまでの点数が取れればOKというゴールを点数ベースで決めて、頑張ってみましょう。
守備範囲を決める
ゴールで決めた点数を取るのに必要な問題集や教科書の範囲を決めてください。問題集や教科書はかなり分厚いので全部やろうとすると、それだけでやる気が削がれてしまいます。
ゴールで決めた点数を取るためには、すべてやる必要はありません。必要な部分だけ自分の守備範囲にすればいいのです。
例えば定期テストで80点の範囲が基本問題の場合、目標点数が75点なら応用問題はやる必要がありません。基本問題を徹底することで確実にゴールとなる点数を取れるようにしましょう。
細分化
守備範囲を1日分の勉強に分けていきます。例えば基本問題35問をテスト週間の14日間で2周する場合、35問×2周÷14日と計算すると1日当たり5問という計算になります。
1日5問であれば、短時間でできるのではないでしょうか。
こうして、設定したゴールから守備範囲を決め、細分化することで、効率的に勉強できます。
睡眠時間は削らない
文部科学省の調査によると授業中、眠くなることがあるかという質問で、「よくある」「ときどきある」と答えた高校生の割合が78.5%と高い数値になりました。十分な睡眠がとれていないことが要因と考えられます。
部活も勉強も忙しいからいつも眠る時間が遅いというのなら、すぐに改善しましょう。人は寝ている間に記憶を整理するので、睡眠は学習内容の定着に重要なのです。
また、睡眠不足だと次の日に眠くなり授業中、集中できません。
睡眠時間を確保するためには
高校生の適切な睡眠時間は「8~10時間」といわれています。しかし、内閣府が行った調査によると高校生の平均睡眠時間は「6時間54分」と、世界の同世代と比べても1時間以上足りていません。
集中して勉強ができるようになるためにも、睡眠時間を確保し体調管理をしっかり行えるようにしましょう。
睡眠時間を固定する
毎日23時就寝、7時起床など、就寝時間と起床時間を決めて習慣化することがおすすめです。時間を決めておくことで、常に時間を意識して行動できるようになり、生活リズムも生まれやすくなります。
勉強時間を朝方にする
部活で帰宅が遅くなると頭も体も疲れています。そんな状態で勉強するのは効率的ではありません。夜はしっかり眠り疲れをとった朝に勉強する朝学習がおすすめです。睡眠時間も確保でき勉強もはかどります。
部活は続けよう
部活が忙しくて、勉強する時間がない場合、部活を辞めるという選択肢が出てくると思います。
部活は楽しいですか?やりがいを感じていますか?そうであるなら、辞めないべきです。自分で決めた部活を辞めてしまったら、きっと勉強も途中で辞めてしまうでしょう。部活が楽しいからこそ勉強も頑張れますし、最後まで部活をやっていてよかったと思えるでしょう。
その時の心理として勉強を言い訳にして、逃げ道を作っていたかもしれません。部活に入ると決めた時、勉強と部活の両方を頑張ろうと思ったのではないでしょうか。
そして、部活を通して学ぶことは多いはずです。先輩や仲間たちとの出会い、部活を通して得た経験はかけがえのないものです。決して無駄にはならないはずですよ。