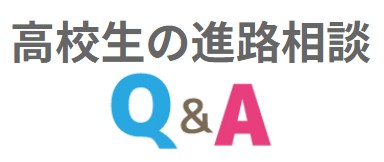Q.すし職人になるために必要な事は?
昔はすし職人というと、修行が長くて厳しいというイメージがありました。
すしは古くから日本で食べられてきた伝統食です。
すしを握る職人さんをすし職人といいますが、腕のいいすし職人さんのお店は、高くてもいつも一杯で、予約が取れないというほどです。
技術をしっかり身に着けて、いずれ、独立するということが当然の世界で、厳しい職人さんたちの中で修業を積み、サラやお鍋などを洗うところから次第に、お客様により近い働き場所となり、最終的に花板と呼ばれるお客さんの目の前ですしを握る事が出来る人になります。
Q.すし職人に資格は必要ですか?
すし職人は職人さんの世界です。
免許や資格などは必要なく、腕1本でのし上がっていく職業です。
すしは職場で初めて習得するもので、雇用主となる寿司屋の職人さんたちのもとで下積みからしっかりと作業し、魚のさばき方、刺身の切り方、盛り付け方、さらに材料の吟味の仕方まで教わります。
調理方法の手順なども次第に学ぶようになり、最終的にしっかりとすしを握れるようになってから、独立される方は独立の道を考えます。
すし職人の資格などはありませんが、調理師、専門調理師、調理技能士などの資格を持っていると、就職については有利といわれています。
ただこれらの資格は、寿司屋に就職してから後、取得する方もいますので、なくてはいけないという資格ではありません。
ふぐなどの場合、ふぐ調理師という特別な資格を取得しなければ扱う事が出来ません。
毒を持っているため、食べていいところ、いけないところ、触れていい部分と触れてはいけない部分などがあるため、その技術、知識を学びます。
この他、衛生面などに気を配り、常に清潔な状態でいなければなりません。
すしは生ものを扱いますし、人の前で握って作るものです。
不潔な状態ではお客様も嫌がります。
Q.すし職人の修行ってかなり辛い修行ですよね?
あるお店ではカウンターで頼んで握りを食べる事の出来る寿司屋で、回転寿司とは違い、かなり費用がとられるだろうと思うほどの寿司屋なのに、異常に安いという所があります。
ここは、あるすし職人養成の学校が営業しているお店で、専門校の生徒が、寿司を握っているから安いのです。
プロが握らなくても、ネタが新しく、またおいしい、安すぎると評判で、いつも満員状態です。
学生が握る事で実際にお客様の前での実習となりますし、お客さんとの会話等、普段できない訓練ができます。
すし職人はとにかく、衛生に気を配り、誰の前に出ても恥ずかしくないようにしておくべきです。
すし職人になりたい方の専門学校なども、現在出ていますので、興味があるようならどのような資格が取れるのか、どのような授業内容なのか見学にいくなり、雑誌等でも調べておくといいでしょう。